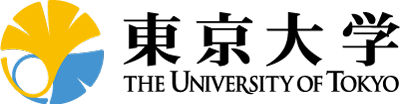中村尚史教授(社会科学研究所)へのインタビュー
鍾 以江(東洋文化研究所)

中村先生、今日国際総合日本学についてインタビューさせていただきます。
実は国際的な日本研究ということを前から考えていまして、「国際日本研究と私」という論文も書いたことがあります。私は二〇〇二年に社会科学研究所に着任して以降、二〇一二年に至るまで一〇年間、社研の英文雑誌Social Science Japan Journalの編集に携わりました。一九九八年に創刊されたSSJJは社研が編集し、オックスフォード大学出版局から年二回刊行されている雑誌です。SSJJの特徴は、社会科学のあらゆる分野から日本関係の学術論文の投稿を受け付けている点にあります。それに対応する形で、編集委員会も法学、政治学、経済学、社会学、歴史学、人類学の専門家から構成されています。しかし論文の審査には、編集委員会全員が参加するため、当然、専門外の論文も読まなければなりません。これまで基本的に経済学と歴史学の論文しか読んでこなかった私にとって、社会科学の他分野の英語論文を、真剣にしかも大量に読むというのは、初めての経験でした。
二〇〇三年にイギリスのシェフィールド大学東アジア研究院に滞在しました。そこで国際日本研究という分野の存在意義、つまり日本人が知らない日本を外から発見すること、が理解できました。そのきっかけにJapan History Group(JHG)を作る気になりました。シェフィールドから帰って、今情報学環にいるJason Karlinさんと一緒にJHGを立ち上げました。Karlinさんは当時SSJJのマネジング・エディターでした。JHGへの参加者は、基本的には社研ではなく外の人です。社研に席を置いた人をベースにして、JHGのある種のプラットフォームを作って、そこにいろんな人を呼んで、今までやってきています。参加者のリストには百人以上います。SSJJが社会科学分野における学際的な国際日本研究の拠点を目指しているとすれば、このJHGは日本の日本史研究と海外の日本史研究との架橋をめざす研究会という位置づけになります。
社研の先生方はよく英語などの外国語を使われると聞きましたがいかがですか?
基本的に社研の中で語学が一番苦手なのは私ではないかと思います。みんな本当にすごいですよ。誰でも流暢な英語あるいはフランス語、ドイツ語をしゃべります。論文も英語で書いています。次元が違う感じがしますね。でもたぶん東大の中では日本史研究でインターナショナルなところは駒場ですね。例えば三谷博先生、おやめになりましたが、日本史研究のなかで一番先頭に立って国際化を推進されてこられたではないかと思います。なので、駒場の卒業生も英語ができます。
日本史の博士学位が取れるところは文学部と駒場ですね。
そうですね。文学部は博士(文学)、駒場は博士(学術)ですが、基本的には一緒です。いわゆる歴史学の場合はこの二つなのですが、例えば経済学研究科では経済史専攻というのがあって、法学政治学研究科では政治史、教育学部にeducational historyつまり日本教育史があります。あと農学部もあります。Agricultural historyです。また駒場には科学史もあります。いろんなところで歴史の研究者が養成されて、なおかつ人文社会系研究科以外のところでは、ある程度国際日本研究に関心があります。そこはアメリカと違うところですね。アメリカでは歴史はヒストリー学部に固まっているでしょう。日本の場合、そのようなこともありますが、それ以外のところにたくさんの歴史研究があることですね。このほうがダイバーシティはあっていいではないかと思います。
東大の一つ大きい特徴は横断的に組織されていないということですね。国際日本学の講演会のポスターなどを大学の中で張るのも難しいです。結局有名な先生が講演されてもオーディエンスはとても少ないです。
なぜかというと、結局もともと東京大学というのが生まれた過程でいくつかの大学が一緒になったわけですよ。例えば医科大学、工科大学、農科大学あとは駒場のほうは第一高等学校とかですね、ある意味寄せ集めで、縦割り意識は非常に強くて、そのような伝統みたいなものがあるのです。これはどうしようもないことですね。だから、社研や東文研のようなハブになる研究所とかは接着剤のような役割をしないといけないですね。実際私たちは法学政治学研究科、経済学研究科、教育学研究科、部分的には文学社会系研究科の、その中の社会科学系の人たちのネットワークのある種のコネクター的な役割があるのかなと思いますけど。一番関係が密接なのは法律と政治と経済です。東文研の場合は文学研究科と駒場ですね。
このたび設立された国際総合日本学ネットワークは、国内の日本研究を海外の日本研究と交流させる目的を持っています。ただ英語に関心を持ってくれる学生と教員は少ないです。特に学生は英語が重要だという意識を持たない場合、教員からのプッシュが必要だと感じます。
それは実は起こりつつあって、特に経済学研究科は英語のみで卒業できるコースを設けています。いまは大学院生にとって英語は必須ですね。
どのような論文がいい論文かは言語によって判断基準が変わります。問題意識もそうです。いくら緻密な実証的な研究でも、海外の日本研究が問題化している国民国家の枠自体を問題として考えないと不十分だと思います。
問題設定ですね。日本の場合、大きな枠組みを誰かに頼る傾向があります。その枠の中でエビデンスを突き詰めていくわけです。それがいい論文だというふうに言われています。たぶんこれまでの欧米の日本史研究にとってもそういう論文は使いやすかったのではないですか?枠組みは自分たちが考えるけど、エビデンスは資料から立ち上げるのがものすごく大変だから、資料を発掘してくれる論文がたくさんあるのが便利でしょう。そのようなところである意味で棲み分けをやってきたではないかと思います。海外の日本研究と日本の日本研究のいいと思われる論文のベクターが違うので。それは今のところになると、すり合わせしないといけないということになってきています。お互いに大変ですね。日本人がその枠組みを考え始めると、その枠組みで資料を切り取っちゃうので、二次利用ができなくなります。その場合プライマリ・ソースに直接にアプローチしないといけないから、たぶん海外の日本研究はものすごく高いレベルを求められると思います。これは大変ですよ。難しい局面に来ているかなと思ったりしますね。だから評価の軸を一本にするということはかなりいろんな意味で難しい問題を引き起こします。ある種のダイバーシティが存在したほうが実は全体的なレベルアップのためには意味があるかもしれません。だから私は国際日本研究に携わる時いつもそう思いますね。例えばアメリカのプレゼンターに対して、日本人のディスカセントを持ってきて、コメントしてもらうのですが、お互いにいい感じになるのです。そちらは新しいある種の枠組みを議論したい、こちらはファクト・ファイディングしたい、お互いもっていないものなので、議論はスムーズに行くのです。あんまりぶつからないで、生産的です。
これから日本人が国際日本研究をやるという話になった場合、そうなってくると思いますけど、もしかしたら困るのはアメリカで研究している研究者かもしれない。自分で史料を探さないといけないし、そこは案外難しい問題だと思いますね。同じようなことは実は日本の外国史研究でも起こっているのです。例えばフランス史の場合、今まではフランス人が書いた詳しい論文と本を上手に使いながら、日本的なパースペクティブでまとめるという形で研究がなりたっていた。ところがフランス人の問題関心がグローバルになってくるので、アイディアだけだと勝負できなくなる。そうすると日本人がフランスに行ってフランス語の史料を読んでフランス人と同じように同じような方法で研究せざるを得なくなる。これはものすごくハードルが高いです。これもある種のグローバル化の影響だと思いますね。要するに英語ベースになることです。例えばドイツ語の研究は英語の方法論で切り取りになる。いわばアングロサクソンの考え方でエビデンスが切り刻まれちゃうので、今までの史料に寄り添ったやり方がなくなっちゃいます。ほかの国の研究者にとっては使いにくくて本当のことが見えなくなります。結局自分でやらざるを得ないということです。国際日本研究はその中の一つなので、たぶん気を付けないといけないです。
それぞれの日本研究の多様さと複雑さを保つのが大事ですね。
もう一つ私たちが知らなければならないのはグローバルな時代は永遠ではないということですね。どこかでまたナショナリズムの時代が来るかもしれない。考えたくないですけど。グローバルの時代がある意味で自由でいいと思います。だから国際日本研究がどんどん盛んになっていいのではないかと思いますが、必ずしも永遠に続くかというとそうでもないのがやはり現実なのです。そのときまた別のふれ方をするでしょうね。歴史ってある意味で繰り返すのです。まさに日本における英語の位置そのものが、そういう歴史ですね。
確かにいまは英語の時代です。ただし、これは実は危ないですよ。何が起きるかというと、社会の中に大きい格差が生じるのです。英語ができる人とできない人が分かれてしまって。そのうち英語の格差が社会的なコンフリクトになるわけです。社会の階層を作るシンボルになってしまうのです。英語ができるかどうかは社会を分割するシンボルになる可能性があります。
今日は、国際日本研究に関して様々なコメントとご意見をいただきましてありがとうございます。インタビューはここで終わらせていただきたいと思います。中村先生、どうもありがとうございました。