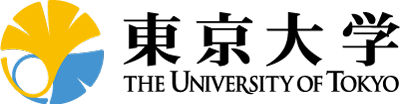名和克郎教授(東京大学東洋文化研究所)へのインタビュー
鍾 以江(東洋文化研究所)

名和先生、今日よろしくお願い致します。主に三つの問題に関して、先生のご意見をお伺いしたいと思います。まず先生のご専門を伺って、それから先生のご専門から見た日本研究に関して、先生のご意見をお伺いしたいと思います。
私の専門は、ディシプリン的には広く言えば人類学、中でも文化人類学、社会人類学と呼ばれている分野です。地域的にはネパールを中心とするヒマラヤ地域です。ヒマラヤは南アジアとチベット高原の間にありますが、より広い地域的専門としては、南アジアのほうが中心です。
まず文化人類学のほうから言うと、日本の文化人類学には独自の歴史があって、戦前から人類学的な伝統はあったのだけれども、戦後に、主にアメリカから輸入された人類学が、今に至る日本の制度化された文化人類学の主流になったという経緯があります。そこでは、文化人類学は異文化研究をするものだという点が強調されました。そのため、戦後の日本の人類学というのは、日本の研究を自分の研究の中心にしない傾向がありました。戦後すぐは海外になかなか出られなかったですから、多くの研究者が日本国内にフィールドを持っていたのですが、基本的には他者を研究するということで、沖縄の研究をしたりしていたのが、大学院生が比較的海外に行きやすくなると、20世紀末か21世紀の最初の頃までは、大多数の人が海外にフィールドワークに行って調査をして、それで博士論文を書いていたと思います。その後は、日本国内での研究も増えてきているという印象はありますが。 特に東京大学の文化人類学研究室の中で、日本研究だけをする人は少数派でした。今はフォークロアの先生がいらっしゃることもあり、日本研究をやる方もいらっしゃいますが、私が大学院生だった頃は、むしろ留学生、特に韓国からの人が日本に来て、東大の大学院で日本の研究をされるということが多かったように思います。中国からの留学生の中には、あんまり日本研究をされる方は、少なくとも東大の文化人類学は多くなくて、むしろ中国の国内の研究をやって、日本で書くという方のほうが多かったと思います。 最近は日本国内の調査で博士論文書いて行く人も増えていますが、ただ、基本的には自文化ではない文化の研究をするという、文化人類学の建前のようなものはまだ何となく生きているように感じます。もう一つ、歴史的には民俗学、フォークロアという学問が、日本で柳田國男以来確立してきましたので、それとのすみ分けということもあったのだと思います。 私の理解では、アジアでこういうタイプの社会・文化人類学が主流になっている国は少ないです。大体、アジアの人類学というのは自文化、自社会研究をする場合が多い。中国もそうですし、インドでもそうです。このあいだ、たまたまカトマンドゥであったヒマラヤ研究の学会に参加したら、「インドの社会学者、人類学者はネパールすら研究しない。インドのことしか研究しない」と批判している若いインドの研究者がいて面白かったですけれども。そういうことで、ちょっと日本の人類学は特異なのです。つまり、日本の人類学者の大多数は、日本以外の専門家である。その中では、日本以外のアジアのことをやっている人が、もしかすると一番多いかもしれないけれども、オセアニアのことをやっている人もいれば、南北アメリカのことをやっている人もいれば、アフリカ、特に京都大学は、アフリカ研究の非常に強い伝統があり、素晴らしい研究者がいっぱいいますし、中東、ヨーロッパ等々、世界中のどこの地域でも大体、専門家が誰かいるという形になっています。面白いですね。
面白いです。
では、日本はアジアの中で違うというふうに、分野の構成になっているということは、先生はどういうふうにお考えですか。それは問題ですか。,
問題というか、歴史的経緯でそうなってしまっていて、これは条件なのだと思います。人類学的には、アジアの中で日本を別扱いしているというより、「自社会」或いは「自文化」と「異社会」「異文化」という対比で考える時に、自文化、自社会の方が日本と曖昧に等置されてきたというのが、実体に近いように思います。例えばイギリスの人類学は自分達が植民地化していった地域でのフィールドワークの成果で大きく発展しましたし、アメリカの人類学は、最初はアメリカ大陸に元々住んでいた、「自分たち」以外の人たちの研究から始まったと思いますけれども、第二次世界大戦までは日本にも植民地人類学と言えるものがあり、戦後は、他文化を研究する学問という前提があって。
これは多分、日本の人文社会科学の中でもやや特異な事態ではないかと思います。例えば社会学と比べてみると、日本の社会学者の中には高度に理論的な議論を展開されている人も沢山いるけれども、それらの方々の多くは、具体的な問題としては日本社会について最も良く論じているように思います。日本社会について書いていて、理論的な議論もする。英語やドイツ語やフランス語の社会学の世界で圧倒的な理論的影響力を持った議論はもしかしたらまだないのかも知れないけれども、海外から社会学者が来たり、或いは自分が海外に行った時に、日本社会の話を、日本社会の専門家として、しかも社会学的に洗練された形で提示出来る研究者は多い。だから、国際的な研究協力関係を構築するのは、相対的に容易であるように思われます。 それに対して、日本の人類学者の多くは、海外に行っても、本当の専門家として日本社会の話ができないという大きなギャップがあります。地域的な専門を同じくする海外の研究者との個別の交流は当然あるけれども、それを超えた交流となると、どうしても限定されるのではないか。では、国際交流をする上ではどちらがいいのかというと、必ずしも人類学の状況が不利であるとばかりは言い切れないとは思いますが、今言ったような条件があるようには思います。理論的な面はどうでしょうか。
理論的な面は、これはいろいろあって難しいですが、日本の人類学にも大まかに言って幾つか伝統があって、例えば東大の伝統と、都立大の伝統と、京都大学の伝統、等々と挙げられます。京都大学は、中に入ってみれば恐らく複雑なのでしょうけれども、外から見ると自分達の学問的な伝統をいうものを持っていて、その中で育てて来た様々な議論を、展開してきている。それに対して、東大の文化人類学は伝統があるようでないように思われる。欧文で書かれた最先端の理論を吸収して、自分のフィールドワークをやって、それで論文を書くというパターンが、比較的多いのです。長期にわたって東大の人類学において議論され、謂わば東大の人類学の伝統の核をなすような論文というものも、どうも見当たらない。逆に言うと、それぞれの研究者の独立性が高いということなのだとも思います。
では、東大の伝統から出発して、例えば英語とかフランス語とかの世界で、現在の人類学の最先端の研究者としてばりばり活躍している人がいるかというとあんまりいない。地域的に、その地域の研究者、その地域を専門とする人類学者としては知られているという人はいっぱいいると思うのですが、それを超えて、世界の人類学界でこの人は引用されるべきだ、理論的に必ず目を通すべきだといわれている人が、輩出されているとまでは言えない。勿論、人文社会系を通して、そういう人がどれほどいるかという問題はあるのですが。言語の問題もありますね。
言語の問題もあります。ここで大きいのは、例えば日本研究もやっていて、理論的にも面白い人が日本語で本を書いたら、海外の日本研究者で日本語が出来る人が、引用するだけでなく、訳してくれる可能性もあるのです。
ただ、人類学者の場合は、例えばアフリカ研究とかネパール研究で面白いことをやっていても、ネパール研究者の人は英語で書けば面白いと言ってくれるかもしれないけれども、基本的に日本語は読まないですから、だから、翻訳されないのです。そこは多分、デメリット。デメリットというか、構造的にはいいものが出ても、なかなか日本語のバリアーを超えられない。 例えばブラジルの研究者がポルトガル語で書いたアマゾンの先住民についての民族誌が大変素晴らしく画期的なものであれば、英語母語の人が訳してくれるわけです。実際に、今や人類学の理論的主導者の一人とも目されているEduardo Viveiros de Castroの民族誌は、英訳を通して広く読まれるようになったものです。日本の人類学の場合は、私から見て大変素晴らしいと思う研究者は何人もいますけれども、当人が日本のことをやっていない限り、なかなかそうした出会いが望めない、ということはあります。数カ月前に東文研で人類学者の公募がありましたね。採用となった学者が、ミャンマーのお坊さんの生活を紹介する本を書きましたね。それを読んでみたのですが、そのような研究は海外、英語とか他の言葉に翻訳して出版したら、いい研究になるのですか。
彼の研究は、十分に高く評価されると思います。国際的に似たようなことをやっている人はいて、例えばドイツのMax Planck Institute for Social AnthropologyでBuddhist Temple Economiesのプロジェクトが走っていますが、彼の仕事は、世界的に見てもこの分野での最良の成果の一つだと思います。
ただ、一般論として、日本語で書かれたものなので、それを直訳しただけでは、英語の学問のスタイルにうまく乗らないということはあるかもしれません。使っている概念や細かな論理展開が英語に移しにくいとか、全体構成のスタイルが英語の学術書としては標準的でないとか。そこで、ものすごく当該の論文とか本にほれ込んでいる人が、これを、大変面白いから、英語圏の人にもそのよさが判るように訳してやろうというふうに訳してくれれば、多分、こうした問題点は上手く解決出来るのですが、そうではなくて、仕事だから訳してというふうになると、英語の学術的な文章としては微妙なものが出来てしまって、何だかやっぱり分かりませんねという話で終わる可能性があるかなというふうには思います。東大出版会、英語の本を出していますよね。
出しています。また、京都の人類学の人達は長年英語でも発信を行って来ました。最近も、私自身は大変素晴らしいと思っている論文集の英訳が京都大学学術出版会から英訳されて出たりしています。そうしたところで、翻訳の問題がいかに解決され、或いはされていないのかは、実際に現物に当たって考えなければいけないと思っているのですが、遺憾ながらまだ積読状態で、自分で確かめるところまでいっておりません。
また東文研の英語雑誌International Journal of Asian Studiesはすごく素晴らしい雑誌だと思います。
ええ。あれは素晴らしい試みだったと思います。アジア研究という枠で、アジア発の、日本語のみならず、アジアの他の言語で書かれた優れたものも翻訳して載せるということもやっていました。僕は昔、あれの編集のお手伝いのような仕事をちょっとだけしましたけれども。
知り合いのアメリカの学者もとても勉強になっていると言っていました。
IJASでは、号を超えた特集企画のようなこともやっていました。中国法に関するシリーズの中にも翻訳論文がありましたし、それから黒田さんがやっているAsian monetary historyのシリーズにも、厳選された論文の翻訳が入っています。網野善彦の翻訳もありました。場合によっては、翻訳の前にイントロダクションを付して、その論文の現在における価値を、英語で学問をしている人達に判りやすく示す、といったことをしていました。そこまでやれば、読んでくれる人は読んでくれて、長期的な学術交流に寄与することになるのだろうと思います。
英語ということでいうと、南アジア研究者は、欧米のみならず、南アジアの学者に主に英語で書く人が非常に多いと言う事情があって、英語で書かないと、そもそも国際的な議論の中に入れないということがあります。だから、南アジアを専門にする日本の人類学者には、英語でも書く人が多いです。 南アジア研究者一般に広げても、過去現在の東洋文化研究所や、東大の文学部、教養学部の南アジア研究者は、皆さん英語でも成果を発信されてきたように思います。この点私はまだまだですが。 それは英語で書くことによって、南アジアの研究者ともコミュニケーションできるという点が大きいと思います。例えばヒンディー語で書くと、読者は限定されますし、私の場合ネパール研究者がなぜヒンディーで、ということになる。しかしネパール語で書くとインドの人はほとんどまず読まないだろう、ということがあるので、やっぱり英語になってしまう。これは植民地主義の遺産、英語帝国主義に手を貸しているのではないかという話もあるのだけれども、現実問題としては英語で書くことが多い。その状態を変えない限りには仕方がない面はありますね。 それでは、先生もご存じの南アジアでの日本研究はどのようなことでしょうか。
南アジアでの日本研究って、僕、あんまりよく知らないですよね。
例えば、先ほど先生がおっしゃったような日本人の人類学者と、海外に日本を対象として研究している人類学者との比較とか、コミュニケーションとかがありますか。
それはいろいろあって。つまり、日本というのは外から見れば他者ですから、日本を研究する人類学者は世界各地にいるわけですよね。当然、欧米でも日本研究の伝統というのはばっちりあって、多くの人が人類学的に日本研究を行っているのですが、意外とそこにコミュニケーションがなくて。
つまり、よくあるパターンは、日本で特に伝統的な村落研究なんかでもそうかもしれないですけど、とりわけサブカルチャーなどの人類学的な研究をやろうという人は、大体、人類学者の所へ来ないで、社会学者の所へ行っちゃうわけですよ。そちらのほうが日本のことを学術的に知っていて、恐らく調査の為の伝手も沢山持っていますから。僕の所へ来たって、日本のことは知らないから。ネイティブとしては知っているかも知れないけど、学者として知っているわけではないし、こいつは使えないということで、なかなかいらっしゃらない。先ほどの話の続きのような話ですが。 昔、例えば人類学のコミュニティが小さくて、それぞれトップ同士が直接の知り合いだった時代には、例えば中根千枝という国際的に極めてよく知られた先生がいると、そこにまず紹介されるとか、或いは中根先生の紹介でお弟子さんの所に行くとか、そういうことはあったのですけど、今はもう人類学者の数が爆発的に世界中増えちゃっていますので、そういう感じでもないでしょうから。インターネットの時代になりましたし、人を探すとすると、やっぱり社会学者で、日本のことをよく知っているという人の所に行くようになっているかなというふうに思います。人類学者が爆発的に増えたというのは、日本ですか。
いや、日本でもそうですけれども、国際的にもそうです。例えば、イギリスの人類学って、ものすごく小さかったのですね、第2次大戦後ぐらいまで。もう全員、顔を知っているみたいな感じだった。今はもう、全員顔を知っているなどというのは絶対に不可能です。世界中の大学が人類学のPh.D.を続々と出しますから。アメリカの人類学会は1万人規模だと思います。
日本でも増えていると思いますけど、日本は学会員が2,000人いないぐらい。でも、世界2位か3位かなんですよ。そうですか。少しお話しが変わりますが、東大における日本を研究している学者は、日本を研究しているというふうに思わない場合が多いようですね。
日本を研究しているというのは?
例えば教育であっても、経済であっても、日本研究じゃなくて、大体は自分のディシプリンの研究者だと。
そうですね。そこは面白い。でも、どうなのですかね。そこは……。
一方で、やっぱりご自分が専門に研究している日本に関する特定の事象については自分が一番よく知っており、一番よく論じているという、「この領域については」という正当なる自負はお持ちなのだと思います。だけれども、日本研究という枠でそれを考えたことがない場合が多い、ということではないですかね。ディシプリンによっては、とりたてて別の地域の○○が専門である、と言わない限り、日本の事象が専門、或いは日本の事象も専門、というようなこともあるでしょう。もう一つは、ただ日本のことをやっているのではなくて、例えば、特定のサブディシプリンの理論動向や、他の地域に関する具体的な研究を踏まえた上で、日本の事例を分析している、さらには日本以外の研究もしている、ということから、必ずしも「日本研究」という枠にはおさまらない、ということも、大いにあるかと思います。 歴史学などだと、もう日本史と東洋史、西洋史って分かれちゃっていますから、これは話が違うのですけれども、教育学や社会学のような、一つのディシプリンで研究科や専攻をつくっている所はそういう感じになるのかなと思います。日本研究を考えるとき、例えば国内の、さっきおっしゃったような研究者と、海外の日本研究者たちと比べると、言語の問題が出てきますよね。向こうは大体、自分の言葉で中国なら中国語で日本について書きます。アメリカは英語、日本は日本語で。それで結局、大きいバリアーになってしまって、同じ日本研究だけど、実はそれぞれ小さい別べつの世界になってしまいます。これについて、先生はどう思われますか。
言語の壁については、一つは研究が進展して、すごく専門の領域が細分化されているということが大きいと思います。かつて、例えばアメリカとかイギリスのトップレベルの東アジア研究者であれば、当然、中国語の文献も日本語の文献も十分に読みこなして、例えば東アジアの歴史という広い枠組の中で自らの研究を展開させていた時代があったように思います。しかし、英語をはじめ各言語の文献が爆発的に増えていますので、超人じゃないととても全部はフォローできないことになっている。そこで、言語的にも、また研究の視野にしても、どんどん狭い領域に、皆さん、行くようになってきているのかなというのが、私はこの領域の専門家ではないですから、外から見た印象はあって。
それから、他のディシプリンがどれぐらいそうなのか分からないですけど、人類学で言うと、人類学の論文の貢献の中で、地域研究的な貢献と、人類学全体に拘わる理論的な貢献というのが相対的に分けられるとすると、理論的に何かを言わないと、今、英語圏の人類学のトップレベルの雑誌にはまず掲載されない。地域研究の雑誌には載せられるのだけれども、地域研究の雑誌に載せられると、人類学者として就職するときにあんまりプラスにならないかもしれない。英語圏の人類学のトップレベルの雑誌が、例えば10くらいあるとしたら、そこに載せるとすると、やっぱり理論的なコントリビューションを明示的に主張していて、民族誌はちょっとしょぼくても、理論的に何か面白いことを言っていたほうが通りやすいということが多分あるように、これも外から見て思います。 そうすると民族誌的にきちんとやることよりは、何か理論偏重になってしまい、流行の議論を一ひねりしたような論文が量産される一方、データというか、地域研究的なものへのこだわりが、人類学の中ではやや弱くなっているような気もするのですね、特に英語圏では。 もう一つ、人類学の場合、日本語で、日本の研究をしている日本の第一線の人類学者の先生方はいらっしゃるのだけど、その多くが英語圏の大学で博士号を取っていたりするので、ここも何かギャップがあるのですよね。場合によってはアメリカに留学したら、本当は別の研究がやりたかったのに、あなた日本人なのだから日本研究をやれと言われて、日本研究をさせられた、みたいな話を読んだり聞いたりすることもありますが、そうすると半分、インフォーマントみたいになっちゃうので、あんまり良くないなと思うのです。もともとやりたくなかった訳ですので。やりたくないですね。
もちろん、そうではない人もいます。はじめから英語圏から日本を見直したかったという人もいるでしょうし、例えば日本出身の人で、アメリカではアメリカの主流社会の研究をやって、博士号を取得した人もちゃんといますけども。
言語の問題に戻ると、結局、誰に読んでほしいか、と、自分の将来に如何に役立つか、なのですよね。例えばアメリカの人類学者で、日本を研究している人が日本語で書いて、それでいい読者を得ることはあるかも知れないけれども、就職とか、自分の昇進に有利であるかというと、きっとあんまり有利ではないと。それから、そもそも英語圏と日本の経験的、理論的な関心のずれのために、いいフィードバックが得られるかも不安だということになると、それをやるのだったら、英語で書いて出世したほうが、と皆さん、思うのじゃないかなとも思いますけど、そこはよく分かりません。 勿論、英語圏出身で、日本語でも書く人もいます。日本に住んでいる人だったりしますけども、日本語で、理論のことはあんまり言わないで、もうほとんどエスノグラフィーとそこから導かれる議論だけを綴った素晴らしい本を日本語で出した先生(注: トム・ギル『毎日あほうだんす』)もいますので。彼は確か日本語で先に書いて、英語で後で出したのですけど、そういう先生もいらっしゃいますので、それは例外がいくらでもありますけれども、傾向としてはそうかなと。 何語で書くかは本当に大きいですけど、やっぱり誰に読んでほしいかというのと、費用対効果があるので。日本の人類学者の中には、日本語でしかほとんど書いていないという人も結構いっぱいいるわけで、それは日本の読者に読んでほしいということでしょう。日本の社会学者も、例えば非常に理論的なものを書く人であっても、もう日本語でしか書かないという方もお見かけします。それはやっぱり日本の読者に読んでほしいのであって、イギリスとか、アメリカとか、フランスとか、ドイツとかの偉い理論家に対して直接けんかを売りたいというわけではないのでしょうね、きっと。本当に喧嘩したかったら、英語とかフランス語とか、ドイツ語で書けばいいわけですから。勿論、「自分が自分の言語で書くのは当然であって、それを読んでいないのは先方の怠慢である」、と言う主張は、全くもって正論ではありますが、現実問題としては、相手の言語で書いていないということは、やっぱり批判はするけど、相手に直接インパクトを与えたいと強くは思っていないのだということなのかな、と思います。なるほど。時間もそろそろですので、最後に、今立ち上げつつある国際総合日本学について、先生のアドバイスをお伺いしたいです。
いや、これは難しいですよね。私のアドバイスはあんまりなくて。
じゃあ、批判でも。
具体的内実は何一つ知らないので一般論で申し上げますと、こうした新たなプログラムの運営は、東大内の構造の問題と関わるので、いろいろと大変だろうなあと思います。これまで人文科学における日本に関する研究の中核を担ってきた伝統ある組織が東大には複数あり、それらの間で様々な経緯もあったことでしょう。また、人文社会系が厳しい昨今、部局単位、さらには専攻単位で、自らを差異化し生き残りのための戦略を立てなければならない状況もあるかと思います。対して東文研は、元々日本以外のアジアについて研究してきた研究所です。
もう一つは、やっぱり英語でどれだけやりたいかということです。日本のことをやるのだったら、日本語でという。わざわざ英語で私はやりたくありませんという人はいらっしゃるかと思います。 とういことで、本当にやる気のある人がうまく集まって、うわーっとできればいいのだけれども、何かそういう感じにならないなという気が、いたします。今、ちょっと具体的なことについて、例えばセミナーとか講演会をつくっています。そのような実際問題としては人があんまり来てくれないです。
来てくれないですね。そうなのです。それは僕も実にそう思います。
いつもは先生が来ていただいて、すごくありがたいですが、広報とか問題ですよね。
広報は問題ですね。ただ、一つのやり方としては、例えば文学部など、東文研以外に来ている人にお話ししてもらうみたいなのは、一つの可能性としてあるかと思います。そうすると向こうの院生さんとかも来るかもしれないしという。先生は来ないかもしれないけれども。
そのようなパターンみたいになっていますよね。去年文学部の先生が講演してくださる場合は学生を連れてきて、海外の先生が講演してくれる場合は、ここの訪問研究員とか、海外の学生が多いですね。結局、そのような分類になってしまって。
そう。なかなか来られないです。ただ、人数的には、例えば僕はハーバードに2013年に行かせてもらいましたけれども、ものすごい有名人でなければ、この手のセミナーには必ずしもそれほど人は集まっていませんでした。例えば5人ということはないかもしれないけど、行って見たら10人とか20人くらいのセミナーだったりすることもよくありました。大変有名な人が来ると、わーっと、もう大きい部屋を取っちゃったり、小さい部屋だったら、満員で廊下にまで人がいる状態になっちゃったりということがありますけども。
長期的には、ディスカッションの質が多分、こうしたプログラムの継続にとっては一番問題なので、よい参加者を確保するというのと、あと、やっぱり日本側からよいコメントできる人が、特に海外から人を呼んだときは、比較的専門が近くて、日本からの具体的で建設的なコメントができる人がいたら、将来的にも「こういう面白い所があるよ」と言ってもらえるのではないかなというふうに思うのですけど。こういうディスカッサント。
ディスカッサントをつくるかどうかにかかわらず、要するにやっぱり発表するということはフィードバックが欲しいわけですよね。いいフィードバック、破壊的なのではなくて、建設的なフィードバックを貰えると、一番嬉しいのだと思います。だから、専門に近い人がいると、多分、セミナーとしてはいいと思うのですけど、なかなかそういう人は難しいなと、今、話を聞いていても。
オーディエンスのことですよね?
オーディエンスですよね。
コミュニケーションがちゃんとできるかどうかという問題ですかね。
日本の学者の場合は、英語の問題もありますよね。それは誰か手伝ってあげればいいのだと思いますけれども。
日本語でもいいですし、それもちょっと工夫したいです。
難しいですね。でも、とにかくいい人が来てくれないと、というのが、お客さんの問題で。
大変貴重なご意見ありがとうございます。では、今日のインタビューはここで終了させていただきます。
そうですか。それでいいですか。何かあんまり大した話じゃなくて、すいません。