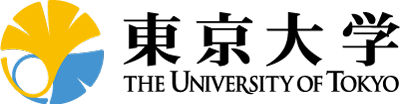インドネシアにおける日本研究
園田茂人(東洋文化研究所&東京大学大学院情報学環・学際情報学府)
2016年10月27日、インドネシア大学で開催されたインドネシア日本研究学会(ASJI)の50周年記念大会に参加した。「インドネシアにおける日本研究の半世紀:過去を振り返り将来を展望する」と題されたシンポジウムで基調講演を依頼され、現地に赴いたのだが、学ぶところが多かった。
まずは、基調講演の内容を紹介しよう。
私は、本学における国際総合日本学がプログラムとして成立した背景、及び現在抱えている困難などを紹介しつつ、日本研究が世界との協働から新たな研究教育を生み出す可能性が高いことを指摘した。そして、香港大学や台湾大学などと共同で実施しているサマープログラムや、インドネシアにおける日系企業研究の事例に出しつつ、日本を外から眺め、それぞれの地域にとっての日本を見ようとすることに、大きな可能性がある点を強調した。
私の次に報告したオーストラリア国立大学のサイモン・アヴェネル(Simon Avenell)教授は、みずからの社会運動研究を振り返りつつ、戦後日本における反公害運動や消費者運動の中に、海外、とりわけアジアとの連帯を求める動きがあったことを強調し、今後の日本研究には、こうした「アジアの中の日本」といった視点が重要になるだろうと指摘した。
最後に報告したインドネシア大学のジュリアン・アルドリン・パシャ(Julian Aldrin Pasha)教授は、日本の経済成長及びその後の混迷から、さまざまな教訓を得ることができるとし、インドネシアの経済運営を考える際に日本研究は格好の教材になることを強調した。パシャ教授が、インドネシアにとっての日本研究の効用を説いたのに対して、私とアヴェネル教授が日本を日本単体として見るべきでないと主張したのは、多分、それぞれが置かれた知的環境の違い以上のものを反映しているのだろう。
基調講演の司会を、私のゼミに出席している本学博士課程学生のウランサリ・スリ・アユ(Wulansari Sri Ayu)さんのご主人で、インドネシア大学で日本研究を牽引するバクティアル・アラム(Bachtiar Alam)教授がなさったのには、奇縁以上のものを感じたが、私にとって印象的だったのは、むしろ、その後に開催されたインドネシア研究者による一般セッションでの報告である。
たとえば、文化のセッションでは、「かわいいキャラ」「もえ」「ケアメン」といった大衆文化に関する、同時代的な報告が多くなされていた。政治や経済のセッションでは、アベノミクスの実態やインドネシアから日本へのケア・ワーカーの「輸出」をめぐる問題など、パシャ教授ではないが、インドネシアにとって役に立つ問題設定が目についた。日本の都市空間における子供の居場所を探った報告や、日本のシングル・ファーザーをテーマに分析した報告など、ハッとする切り口からアプローチしているものも少なくなかった。
もっとも興味深かったのが、インドネシアにおける日本研究の歩みを振り返った、2つの報告である。
1つはヒマワン・プラタマ(Himawan Pratama)氏の報告で、1990年代以降の、インドネシア大学日本研究プログラムで提出された学位取得論文のテーマを分析したもの。プラタマ氏によれば、従来、言語や伝統文化に傾斜したテーマが年代とともに徐々に多様性を増し、その時々によって人気のあるテーマは異なるものの、最近では日本の大衆文化や経済状況に関する関心が強まっているという。
もう1つは、ナニ・スナルニ(Nani Sunarni)氏による、インドネシアにおける日本研究の制度化をめぐる報告で、プラタマ氏同様、関心の多様化が進むと同時に、研究機関がジャワ島以外にも拡がりつつあること、それゆえインドネシア国内での情報共有が重要になりつつあることが指摘された。
これらの報告は、日本をめぐる視線がインドネシアという磁場によって形成されており、これが歴史的に変化していることを示唆している。青木保氏や船曳建夫氏は、日本における日本人論の歴史的推移を問題にしたが、「インドネシアにおける日本人論受容の歴史的推移」といったテーマも十分に研究テーマとして成り立つはずことを、この2つの報告が示している。実際、報告の多くはインドネシア語で行われていたが、これも、日本研究がインドネシアに根づき、研究の「現地化」が進んだことを意味している。
報告を聞くことはできなかったが、大会では「イスラム・オタク共同体」といった報告テーマも準備されていた。配布された報告要旨集によれば、日本のコスプレを愛好するファンが、ジャカルタ、スマトラ、マカサー、マレーシアへと拡がっており、彼ら・彼女らが「イスラム・オタク共同体」と称する団体を作って活動しているという。そしてニューメディアを駆使しながら繋がっているようだが、この研究などは、日本研究なのか東南アジア研究なのか、判別がつかない好例だ。
日本をめぐるハイブリッドな研究を広く世界と結び付け、そこから新しい知を紡ぎ出す。私たちは、多分、そんな時代を生きているはずだ――今回のインドネシア訪問で、そんなことを再確認した。