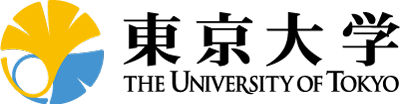サマープログラムを振り返って
園田茂人(東洋文化研究所&東京大学大学院情報学環・学際情報学府)
このエッセーも、通常より執筆時期が遅れてしまった。8月、9月と4つの(合同)サマープログラムを実施することに忙殺され、これに集中講義や2つの国際学会出席と、それ以外の用事も重なったからだが、いつものことながら、プログラムに参加した学生以上に、これをデザイン・運営する私たちの方が多くを学ぶこととなった。
香港における「日本」をテーマに、香港大学と東京大学の学生が同じ宿舎に寝泊まりしながら各種活動に参加する香港大学との合同サマープログラム。東京ラウンドとソウルラウンドの2つを 設け、それぞれに日本と韓国の現実を多角的に理解できるように設計されたソウル大学との合同サマープログラム。中国における日本企業に焦点を当て、企業が国境を超えた後どのような現地化のための努力をしているのかを、日中の学生が一緒に考える北京大学との合同サマープログラム。それに「戦後日本」をテーマに、午前中の講義と午後のフィールドトリップを組み合わせて行われた国際総合日本学プログラム主催によるサマープログラム。パートナーの有無やその関与の仕方・程度、活動のバラエティーや参加学生の特徴、実施時期、東京での活動の有無など、それぞれに異なるものの、すべてのプログラムが日本を意識したものとなった。そうでないと本学の学生が参加しにくいという以上に、本学が世界のパートナーを相手にプログラムを作ろうとしようと、どうしても日本に関わったプログラムにならざるをえないというのが実際のところである。
では、私たちにとって、どのような学びがあったのか。最大の学びは、日本の内外における日本をめぐる異なる眼差しの存在だ。
2016年10月1日の『日本経済新聞』でも紹介されていたが、北京大学では現在、日本の企業文化論が人気だという。実際、上述の北京大学との合同サマープログラムを実施してみて、これを実感した。日本企業にとって当然のいくつかの事柄が、現地学生にとって目新しく、企業担当者の説明に食い入るように聞き入るのである。
北京大学との合同サマープログラムの冒頭で、中国人学生に聞いてみると、その多くは日本企業というと「労働負荷が高く」、「職場の雰囲気は閉鎖的」で、「長期安定雇用のためにダイナミズムに欠ける」といった否定的なイメージを抱いていた。しかし実際に職場に出向き、工場やオフィスの雰囲気を経験してみると、ずいぶんと評価が異なるようになる。特に日本企業がもつ独特なコミュニケーションと商品・製品開発のあり方に関心が抱かれたようで、どうして日本企業が継続的に新しい商品・製品を開発できるのか、大いに感得したようだった。
また、国際総合日本学のサマープログラムでは、戦後の日本を理解するためのいくつかのキーワードを用意し、出講講師の授業とフィールドトリップを組み合わせたが、予想以上に学生の反響が大きかったのが、本田由紀先生の貧困をめぐるセッションだった。私たちは本田先生が戦後の教育についてお話しになると思っていたのだが、その意味で本田先生のセッションには二重に、そしていい意味で裏切られたといえる。多くの海外の学生は、戦後日本の歴史は貧困との決別の歴史として捉えていたのだが、現在も依然として貧困の問題は存在しており、それどころか貧困はなくなったと思いこむことが貧困の存在を隠ぺいしているのだとする本田先生の指摘が、プログラム学生の心に突き刺さったようだ。
企業の問題であれ貧困の問題であれ、多くの日本人学生・研究者には「当然」の事柄かもしれない。しかし、海外の学生・研究者が同じように日本を見ているとは限らず、私たちにとっての「当然」が新しい発見となることは少なくない。そこに、新しい研究・教育の可能性が存在することは、国際総合日本学の立ち上げ時に予想・予期されていたこととはいえ、実際にこうした光景を目撃することは、実に楽しい。
もっとも、こうした彼我の認識ギャップを炙り出すプログラムを運営してくれるスタッフは、依然限られており、個別の講義にご協力いただける先生は見つかっても、プログラムを設計・運営してくれる先生はなかなか見つからない。そのため、どうしても特定のスタッフに負担がのしかかってしまう構造は、ここ数年変わらない。
何より困るのが、本学と世界のパートナーの間にある、学事暦のギャップである。上述の3つの合同サマープログラムはほぼ8月一カ月に集中し、国際総合日本学のサマープログラムの開催時期については、参加学生たちからも「もっと早く実施できないのか」という声が挙がっていた。認識のギャップは研究教育にとって追い風になっても、学事暦のギャップはそうはならない。私たちの奮闘は、かくして続くこととなる。