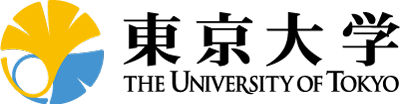続・サマープログラム
園田茂人(東洋文化研究所&東京大学大学院情報学環・学際情報学府)
さて、前回のエッセーの最後に、「(サマー)プログラムを作ることによるメリットは何か。そうすることで何か研究上の収穫はあるのかと問われると、体調が良い時には『ある』、体調が悪いときには『ない』と答えることにしている」と書いた。なぜ、そうなのか。
体調が悪いと、どうしても自分のやっていることを、近視眼的に評価しがちになる。学生のためと思ってプログラムを作り、多くの時間と労力を割いても、学生たちがどのような成長を遂げるようになるかは、すぐにはわからない。それどころか、大学の運営費や外部者の寄附を得てプログラムを運営しても、「これくらいのことしてもらっても当然だ」といった態度を見せる学生もいる。「親の心、子知らず」というわけである。
もっとも、こちらに体力的・精神的な余裕があれば、これも仕方ないと諦めることもできるし、長期的投資であるはずの教育への信念はそう簡単に揺るがない。何より、プログラムの際に聞いた研究者の講義から学ぶことも多いし、フィールドトリップや課外活動から学生以上に刺激を受けることもある。
筆者にとってプログラムを作ることの最大のメリットは、そうすることで、何が問われなければならないかを真剣に考えざるを得ない、というものだ。
魅力的な授業をしてくれることは前提だが、では誰に、どのようなテーマで話をしてもらうかは、どのようなテーマをこちらが想定しているかに依存する。香港大学との合同サマープログラムでは”Understanding Asia and Japan through Hong Kong”、台湾大学との合同サマープログラムでは”Understanding Taiwan and Japan in Global Settings”といったテーマを設け、前回のエッセーで述べたように、今年の国際総合日本学研究ネットワーク主催によるサマープログラムでは「日本の戦後を考える (An Inquiry into Japan’s Postwar)」をテーマに掲げているが、これもこのテーマが現在、日本研究にとって重要なものだと考えているからある。
実際、これらのテーマが時宜にかなったものであるかどうかは、学生たちの反応を見ればすぐわかる。卒業のために履修しなければならないわけでもないし、何よりわざわざ海を渡ってくる/いくとなれば、テーマがよくなければ、そもそも学生は集まらない。
学生の食い付きのよいテーマは、それだけ深掘りが可能なテーマということであり、こうしたテーマを探しだせるかどうかは、プログラムを作る側のセンスや能力に大きく依存する。逆にいえば、みずからの研究にフィードバックするという意味では、プログラムの作成・運営は、研究者養成のための、一種のオン・ザ・ジョブ・トレーニングといってよい。
もっとも、東京大学が置かれた現在の状況からすれば、サマープログラムを作って運営するのは、相当な物好きか暇人だと見なされるだろう。そんな時間があれば自分の研究をしている方がよいし、プログラムを運営しないと研究費が捻出できないような状況にもない。通常業務から解放される夏くらいは、自分の研究に専念したいと考えるのも当然といえば当然だ。
しかし、こうした「効率的な発想」は、結果的にみずからの教育研究の射程を狭め、多くの潜在的支援者を獲得する機会を失うことになりかねない。そればかりか、どんな学生が集まってくるかわかならい状況でプログラムを運営するのは、実に刺激的な経験である。
国際総合日本学は、伸びしろが大きい研究領域である。
筆者は最新号の『UP』に寄稿した拙文で、以下のように述べた。「従来までの中国研究は、観察対象者の『中へ』入り、内部の視点を獲得することが重要だとされてきた。そのために中国語を習得し、中国人研究者と意見交換をし、中国事情を深く理解することが重要だとされてきた。ところが現在の中国研究の困難は、・・・・内部の視点と外部の視点ばかりか、外部間でも視点のズレがあり、見る者によって語られる中国像が大きく異なる点にある」。
同じことは日本研究についても言える。サマープログラムを実施することで、国際総合日本学の抱える困難と可能性を確認することになるだろうが、その報告は、プログラムが終わる9月以降になる。